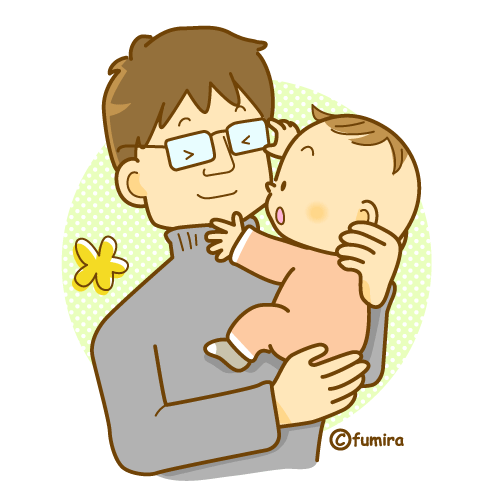「男の子だから言葉が遅い。」
ということは昔からよく言われることですが、実際のところはどうなのか調べてみました。
まず、初語(初めて出た意味のある言葉)についての調査では
 厚生労働省「乳幼児身体発育調査」2010年 7,652人
厚生労働省「乳幼児身体発育調査」2010年 7,652人
7~8か月で2.2%、12〜13か月で57.6%、14〜15か月で79.1%、17〜18か月で89.1%、18〜19か月で94.7%が単語を話している。平均12.2か月。
 吉岡豊ら「初語の意味内容と表出時期について」2012年 228人
吉岡豊ら「初語の意味内容と表出時期について」2012年 228人
全体平均12.7±2.8か月、男児13±3か月、女児では12.4±2.5か月、90%が15か月までに初語が認められた。
わずかに、男の子のほうが初語が遅い結果になっています。
1歳児健診の時点で、男の子でも女の子でも意味のある言葉が出ていない場合は、注意深く保健師さんと見守っていくようにしましょう。
また、育児相談などを勧められた場合は相談に行くことを検討してみましょう。
次に言葉が出てからの言語発達の男児女児の差について研究をみてみましょう。
 藤原雅子ら「1歳代の言語発達 : 1歳0か月から1歳11か月の表出語彙」2005年310人
藤原雅子ら「1歳代の言語発達 : 1歳0か月から1歳11か月の表出語彙」2005年310人
1歳代の獲得語彙数は、1歳から1歳7か月までの性差はない。1歳8か月以降の獲得語彙の数は、女児の方が早期に増え、男児はゆっくりだが名詞や動詞の割合には差はない。
 Teemu Toivainenら「Sex differences in non-verbal and verbal abilities in childhood and adolescence」2017年14,187 人
Teemu Toivainenら「Sex differences in non-verbal and verbal abilities in childhood and adolescence」2017年14,187 人
男女の双子の研究で、4歳までは女児が早いが4歳以降は男児が女児に追いつく。発達段階にわたる非言語能力と言語能力における性差は無視できる程度である。
 山下由紀恵ら「初期言語発達における性差, 利き手要因の分析」1994年669人
山下由紀恵ら「初期言語発達における性差, 利き手要因の分析」1994年669人
2歳までは女児が3か月ほど表出が早く、その後男児が追いつくことを繰り返す。2歳1か月~2歳4か月で一時的に男児が逆転し、2歳5か月~2歳8か月には差がなくなる。遅れは3か月程度で、2歳1か月~2歳4か月頃には女児に追いつく。
以上から、男児女児での言葉の発達の過程で違いはあるようです。
しかし「男の子は言葉が遅いの?」という疑問については、
それぞれの調査から「男の子は、言葉の遅い」とは明らかには言い切れないようです。
子どもの言葉の発達については、男女の差もわずかにあるようですが個人差がとても大きいです。
周りの方に「男の子は言葉が遅いから大丈夫よ」と言われていたとしても、保護者の方が「なんだか、うちの子は言葉が遅い気がするな」と不安に思われているのなら、相談する目安の時期に3歳児健診はちょうどいい機会と言えそうです。
参考文献
厚生労働省(2010)乳幼児身体発育調査<https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001t3so-att/2r9852000001t7dg.pdf>2023.8.31アクセス
吉岡豊他(2012)初語の意味内容と表出時期について<https://core.ac.uk/display/70371767?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1>2023.8.31アクセス
藤原雅子他,1歳代の言語発達 : 1歳0か月から1歳11か月の表出語彙,九州保健福祉大学研究紀要,2005
Teemu Toivainen他(2017),Sex differences in non-verbal and verbal abilities in childhood and adolescence<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160289616303154>2023.8.23アクセス
山下由紀恵他,初期言語発達における性差, 利き手要因の分析,島根女子短期大学紀要,1994