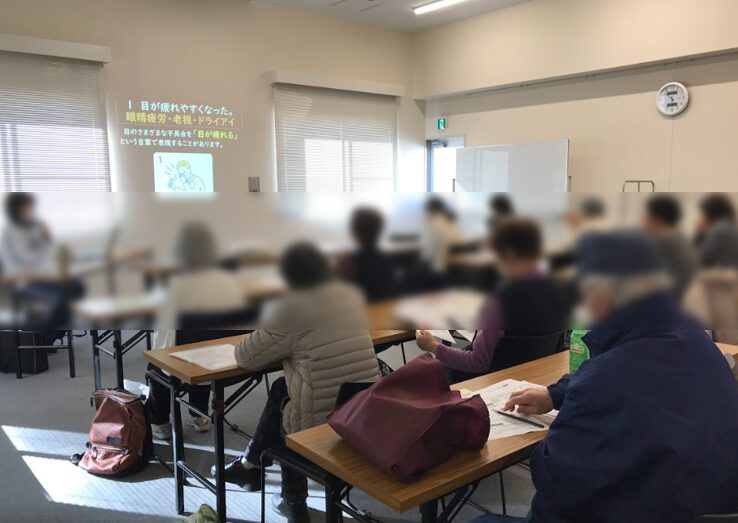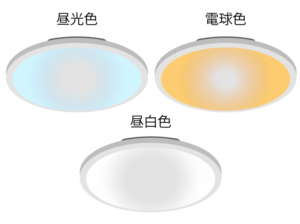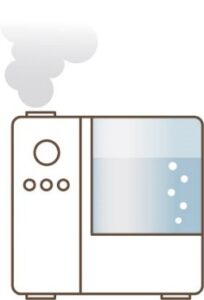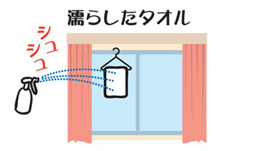令和8年(2026年)の輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
旧年中は、くらしき健康福祉プラザ 視能訓練室をご利用いただき、またこのブログをご覧いただきまして、誠にありがとうございました。
昨年の活動を振り返って
昨年(令和7年)は、私たち視能訓練室にとって、地域の中に飛び出し、多くの皆様と直接つながることのできた実り多き一年でした。
- 「ロービジョンサロン」の開催
見えにくさを抱える方々が集い、日々の工夫や悩みを分かち合う場として定期的に開催いたしました。同じ境遇にある仲間と出会い、共感し合える時間は、参加された皆様にとっても、私たちスタッフにとっても温かいひとときとなりました。
➡ 4月、6月、8月、12月 のブログはこちら
- 「こどもの目の日」イベントの実施
6月のイベントでは、多くのご家族にご参加いただき、近視予防や目のケアについて楽しく学んでいただきました。
➡ こどもの目の日のイベントに関するブログはこちら
- 小学校への出前講座
倉敷市内の小学校へ伺い、学校保健委員会で「メディアとの上手な付き合い方」や「近視予防習慣の大切さ」をお伝えする機会をいただきました。未来を担う子どもたちの目の健康を守るため、現場で直接お話しできたことは大きな一歩でした。
※倉敷市内の小学校への出前講座を実施しております。また、各校の取り組みに合わせた資料提供等をしておりますので、ご希望の場合は、お問い合わせください。
今年の抱負:皆様の「生活」を支えるパートナーとして
昨年の活動を通じて改めて感じたのは、「見え方の支援は、その人の人生そのものを支えること」という原点です。
「見えにくさ」によって生じる不安や不便は、人それぞれ異なります。
だからこそ、私たちは地域での相談支援を担当する視能訓練士としての経験を活かし、皆様お一人おひとりの「こうありたい」という願いに耳を傾け、その人らしい生活を続けるための「伴走者(パートナー)」でありたいと強く願っております。
本年も、専門的なサポートはもちろんのこと、皆様がほっと安心できるような温かい場所づくりに努めて参ります。
ブログでの情報発信について
本年も引き続き、皆様の日々の暮らしに役立つ情報をブログでお届けしてまいります。
- 更新頻度: 毎月2回(中旬・下旬ごろ)
- 内容: 見え方に関する役立つ知識、便利グッズの紹介、イベントや講座の報告など
お時間の空いた時に、ぜひお読みいただけると幸いです。
ご相談・お問い合わせ
日常生活での見えにくさにお困りの方、またそのご家族様、どうぞ一人で悩まずお気軽にご相談ください。
昨年のサロンのように、誰かと話すことで心が軽くなることもあります。
倉敷市民の方でご相談を希望される方は、まずはお電話またはメールにてご連絡ください。
電話: 086-434-9885
(火~土曜 9:00~17:00 祝日除く)
E-mail: miekata@kgwc.or.jp
※倉敷市在住の方を対象に相談支援をおこなっています。
来所が困難な場合は、スタッフの訪問も可能です。
本年が皆様にとって、明るく希望に満ちた一年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
くらしき健康福祉プラザ
視能訓練室 スタッフ一同