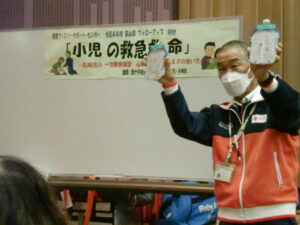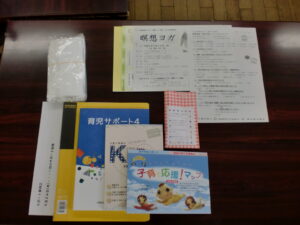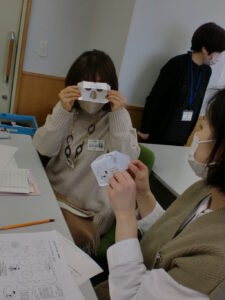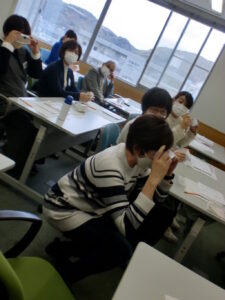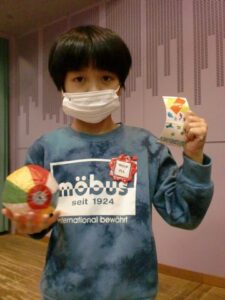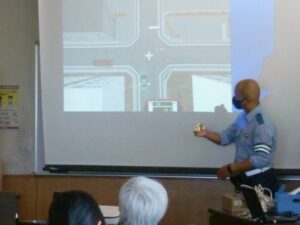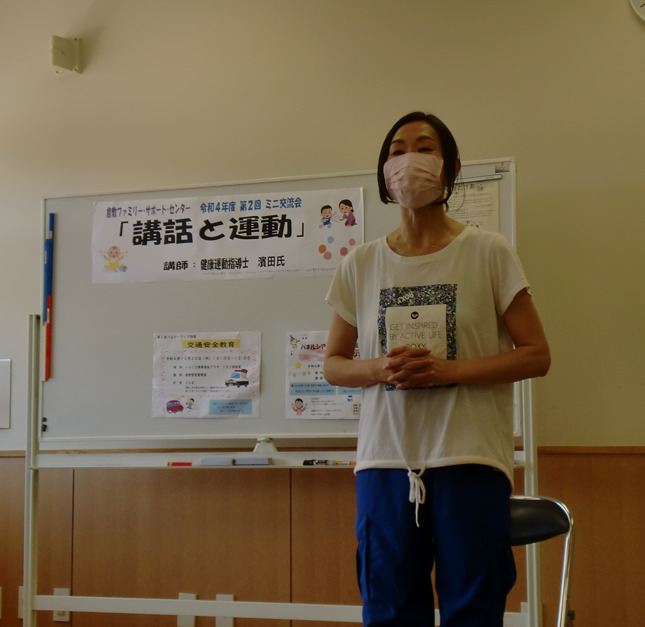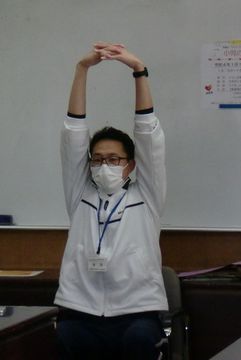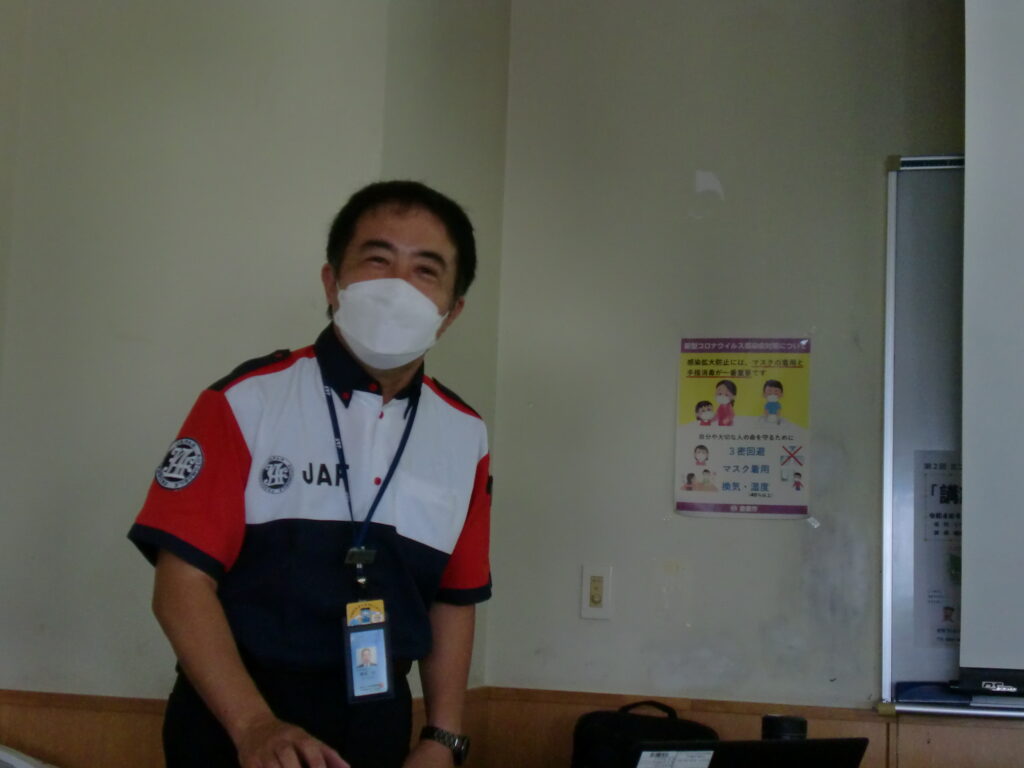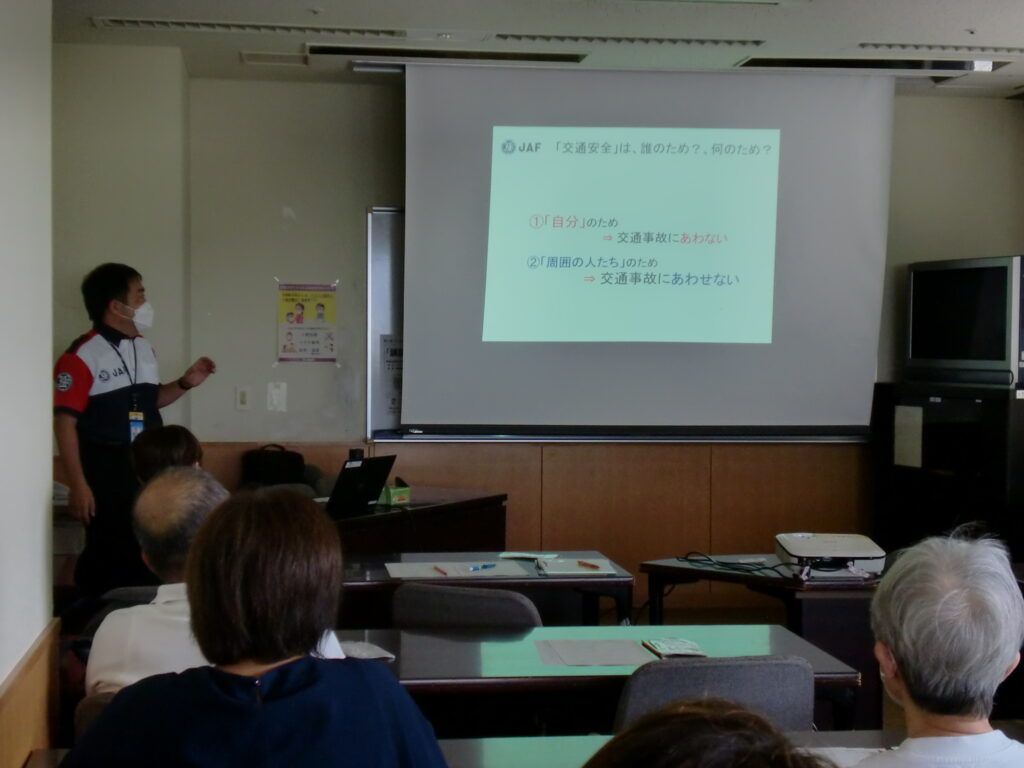令和5年度 第1回フォローアップ研修を5月16日(火) 10:00~12:00
201研修室で行いました![]()
「子どものメンタルヘルス ~こころの声に耳を傾けて~」
川崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉学科 田渕泰子先生
研修は、先生の自己紹介から始まりました。
アナウンサーとソーシャルワーカーの2つの天職に恵まれたご経歴ということも
あり、わかりやすく「こころの病」についてお話いただきました。
精神疾患(こころの病)は、脳の機能的な障害や器質的な問題によって生じる疾患で、
遺伝子+環境要因によって発症するそうです。生涯を通じて、5人に1人が発症、
思春期にその兆しがあり、誰にでも起こり得るありふれた病気 であることを学び
ました。
こころの不調になったら…
1.休養する
2.相談する
3.視点を変える
日常生活の中ですぐできる対処法も教えていただきました![]()
![]() サブ・リーダーNさんからの感想
サブ・リーダーNさんからの感想![]()
元アナウンサーであられた田渕先生の美しい声に聴き惚れながら、先生の経歴・
日本の精神疾患の現状をお聞きしました。
先日、新聞でも大きく取り上げられていましたが、若い世代の自死率が年々、
増加しているという現状は大変心痛むものがあります。その原因の7割以上が
健康(精神疾患)に関することで、精神疾患は誰にでも起こり得るありふれた病気で
あることを知りました。精神疾患の中でも「統合失調症」という病、耳にはしてい
たものの、浅い知識しかありませんでしたが、今回、発症の多い年齢、原因、症状、
経過、治療法等、多くのことを教えていただきました。
100%防げることではなくても、思春期の子どもを持つ母として、日々の体調を気遣い
(睡眠がしっかり取れているか) 栄養のある食事、ストレスを溜め込まない生活が送れ
るようにサポートしていきたいと強く思いました。
そして、先生が言われていたように、人が人の温もりを感じながら、今あるそのまま
自分を「これが私です」と堂々と生きていく地域社会になるよう、日々穏やかな気持
ちで過ごしていきたいと思います。
![]() アドバイザーより
アドバイザーより![]()
今年度初めてのフォローアップ研修で、19名の方が参加してくださいました。
先生のお話から、お互いの違いを認め、尊重し合える関係性を保てるように職場
や家庭でも努めていきたいと再認識しました。
![]() 次回講習会・交流会
次回講習会・交流会![]()
令和5年6月13日(火) にミニ交流会「目の予防の話」が201研修室であります。
必須講習(事故防止)です。参加ご希望の方はセンターまでご連絡ください。